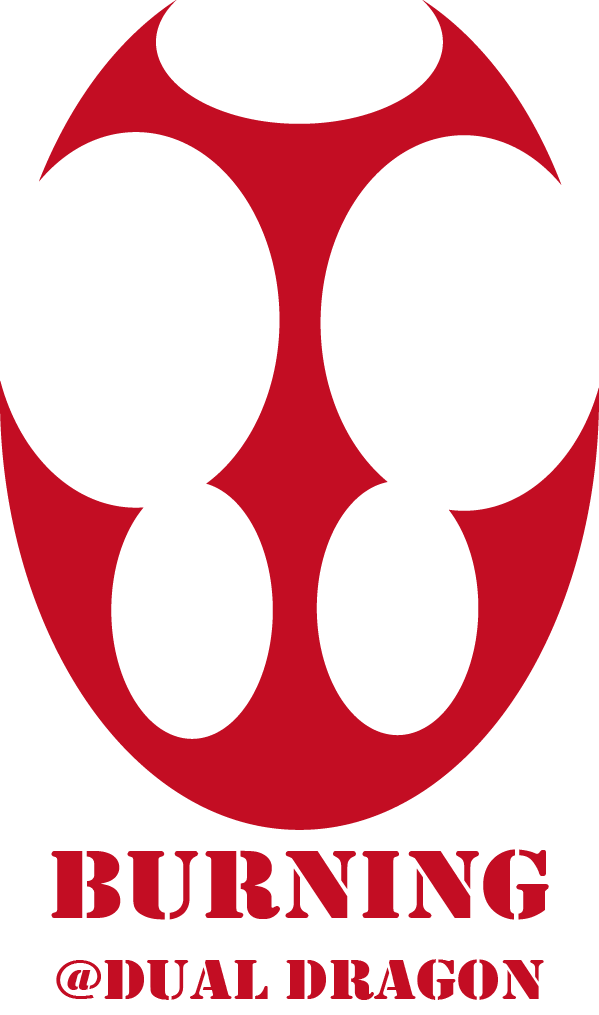2015/10/05 21:04
当初、サモア戦は、フィジカル勝負という見方が大半だった。ジャパンを警戒しすぎ、ナーバスなサモアは、強みを出すことなく沈黙した。アタックも二個一といわれるスネークプレイも単純すぎるのと、サードプレイヤーとの距離がありすぎ、連続したアタックとはならず、フィジカルは封殺された。対して、反則数19とジャパンのアタックについて行けずに、反則の山を築き,得点を与え、リズム、主導権を渡し続けた完敗であった。
ジャパンは、先のスコットランド戦からキックが、10から31へと増加し、オフロードは、6から3へと減少した。ジャパンのラグビーは、非常に理詰めであり、機能すればどの敵であっても勝つことが出来る射程圏に入れている。高速アタック、アタッキングラグビー、世界一のフィットネス、と当初掲げていた。トライをたくさんとって勝つと誤解してはいけない。高速アタック、NZなどとはちがい、オフロードパスを繋がず、ジャパンはラックに勝機を見いだした。立って繋ぐことが体力的に厳しいジャパンは、アタックシェイプやランラックといわれる、一旦ラックにして2秒以内にリサイクルして、アタックし続けるという戦略を選択した。オフロードパスは、オフサイドラインも形成せずに、ボールを動かし続け、敵に反撃の意図を作らせないことにあるが、ラックは、オフサイドラインを形成させ、敵を一旦出来たオフサイドラインへ下げた状態で、スペースを作り出してアタックする。ラック形成には、スキルとフィットネスとブレイクダウンと呼ばれる敵との厳しい攻防が余儀なくされ、ペナルティを犯す危険性が両チームに存在している。
ジャパンは、後者のラック戦略を採用した。しかも、ランラックと呼ばれる、走るようにラックを作るといわれる、いわば、オフロードパスよりも威力のある戦略を作りつつある。アタックサイクルを素早くすることで、トライを生むというのではなく、ジャパンはまだ、トライを量産していない。敵の反則を量産している。ラグビーは、最終スコアを競うゲームであり、トライの数ではない。ジャパンのランラックを繰り返すことで、敵は、たまらずペナルティを起こしてしまう。ジャパンが、ポゼッションを有意に獲得すればするほど、蟻地獄へと陥る。スコットランドは、前に出るディフェンスと、厳しいプレッシャーをブレイクダウンにかけて、ジャパンを封じた。サモアは、南アフリカと同様、待ってディフェンスを揃えて、受けたため、ジャパンが思い通りに試合を支配した。
高速アタック、アタッキングラグビー、アタックシェイプというフラッグは、ランラックという肉を切らして骨を断つ戦略であった。ジャパンの神髄である。