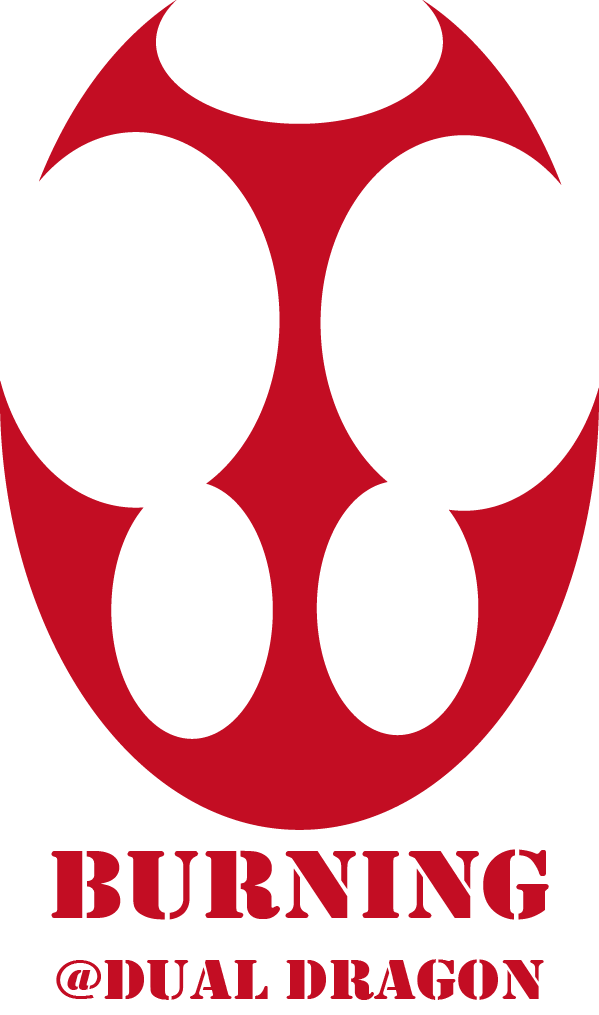2016/06/26 10:08
東京味の素スタジアムで、欧州の強豪国の一つであるスコットランドと対戦したジャパンは、16対21で逆転負けをした。前半は13対9とリードするも後半、反則から確実にPGを決められ、追い上げる足(体力)もなく、敗北した。ジャパンは、トライ1、対するスコットランドは、ノートライだった。
終始ジャパンがゲームの主導権を握っていたかに見えたが、スコットランドペースに感じた。リードされるも、80分勝負というのが腹からあったのであろう。リードされるも、ペースを崩さず、ぴったり追走してきた。
後半、チーム主将であるレイドローが投入されると、さらに、ゲームテンポを落として、じっくり着実に反則を誘い、自身のPGで勝利に導いた。途中から出場でのキッカーの交代にも動揺することなく、冷静沈着にゲームをコントロールして、●(黒星)を○(白星)にひっくり返した、彼のゲームコントロールは特筆すべきでものであり、日本のチームが一番学ばなければならないスキルである。
日本のハーフは、優れたスキルを持ったプレイヤーが多い。どのハーフも個性があり、パスが上手であり、まじめで勤勉なので、好みのハーフである。しかし、ゲームコントロールという点では、国際レベルとの差は大きい。ラグビーは意志決定のスポーツであり、すべてのプレイヤーは、常に意志決定を迫られている。日本のプレイヤーも意志決定するレベルは向上した。ゲームコントローするものの意志決定は、欠けている。重要なことは、ゲームメイクをするプレイヤーの重要性である。ゲームを勝利に導く意志決定、戦術を選択する意志決定、ゲームをコントロールする意志決定者は、ごく僅かしかおらず、育っていない!
これは、コーチングスタイルの問題であり、プレイヤー自身に問題は少ない。コーチングの問題である。スコットランドも疲れていたが、ジャパンも疲れていた。終盤において、仕留めきる時間帯で、体力的な負荷の高い中途半端なシェイプもどきを使いゲームのテンポを上げようとしていたが、逆に、孤立しチャンスの芽を摘んでしまった。例えば、ポッドを利用して、ゲームテンポを落としても、確実にボールキープして、反則を誘う。疲れ切ったところを仕留めきるなどのゲームメイクが必要だった。ジャパンは、国際レベルでも通用する時間帯を作れることから、スキルレベルは向上している。これは以前から。
coaching 2.0で常々いっている、コーチングのスタイルを変えないことには、「あともう少しだったのにね」というゲームは続く可能性がある。台本どおりのプランを遂行するのには力を発揮するが、ラグビーゲームを読み、ラグビーゲームをすることは苦手である。
コーチングスタイルを早く代えて、ジュニア世代から育成に取り組むと、常に勝利をする可能性がある。トップリーグから、海外のコーチに接するところから、ラグビーゲームを学ぶには遅すぎる。
コーチングスタイルを、アップデートではなく、アップグレードするぐらいのコーチングスタイルの変換が必要である。
coaching 2.0

コーチングスタイルを早く代えて、ジュニア世代から育成に取り組むと、常に勝利をする可能性がある。トップリーグから、海外のコーチに接するところから、ラグビーゲームを学ぶには遅すぎる。
コーチングスタイルを、アップデートではなく、アップグレードするぐらいのコーチングスタイルの変換が必要である。
coaching 2.0