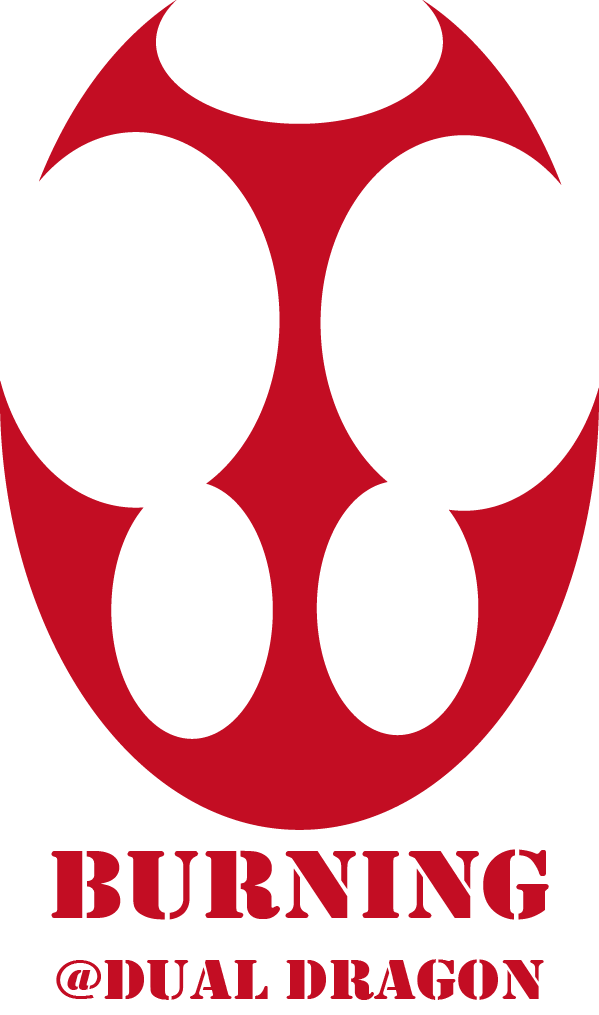2016/07/29 20:16
スポーツ庁が、さらに総合型地域スポーツクラブを推進している。今度は、大学の資産をも巻き込んで、より一層その推進に躍起となっている。20年ほど前の総合型地域スポーツクラブと言われ出した時期にドイツのクラブの実情を期した報告を見た記憶がある。総合型地域スポーツクラブは、ドイツなどの欧米のスポーツクラブがモデルと言われていたので、非常に興味を持った。
そこで報告されていた数値は、総合型地域スポーツクラブといわれる、3種目ほど集まったクラブは、むしろ少数であり、その他、1ないし2種目の括りでいうなら「小規模クラブ」が圧倒的多数であった。なにも、欧米型スポーツクラブ、すなわち総合型地域スポーツクラブがポピュラーな形態ではなかったのである。
むしろ、本当のところは、学校に所属している運動部の方が、総合型地域スポーツクラブと言うにふさわしいのである。学校には、スポーツに止まることなく、文化系、音楽系、理科系、・・・と言われる、実に多くの魅力的なプログラムが用意されている。この形態を、なんと分析するのでしょうか?まさに、総合型地域スポーツクラブといえるのである。
まあ、色々問題、課題がありますが、ここでは論じませんが。
日本で総合型地域スポーツクラブが推進されることで、同好の縁で結ばれた小規模のクラブの淘汰が心配である。基盤である活動の場が制約されかねない。多様性文化が瓦解され、汎用性では、面白み、活力、独創性、そこから生まれるかもしれないイノベーションという破壊力が、阻害されるのではと心配である。
RUGBY-JERという取り組みも、権力、組織、というアンチテーゼとして個でどこまで闘えるのかという挑戦でもある。個が埋没せず、権力,組織に翻弄されずに、尊厳を保つ。個が、個としてあり、活躍できるように。
クラブという強い紐帯で結ばれたクラブが育つことを願っている。
恩師は、クラブの語源は「ゴルフクラブは、昔、一本一本の枝が寄り集まり一本にまとめられたものが、クラブと呼ばれた」と教えられた。
ムリに、総合型にすることもなく、やりたいというスポーツを支援することこそ大事だと思うのだが。少数派も、大事なのではなかろうか。
日本で総合型地域スポーツクラブが推進されることで、同好の縁で結ばれた小規模のクラブの淘汰が心配である。基盤である活動の場が制約されかねない。多様性文化が瓦解され、汎用性では、面白み、活力、独創性、そこから生まれるかもしれないイノベーションという破壊力が、阻害されるのではと心配である。
RUGBY-JERという取り組みも、権力、組織、というアンチテーゼとして個でどこまで闘えるのかという挑戦でもある。個が埋没せず、権力,組織に翻弄されずに、尊厳を保つ。個が、個としてあり、活躍できるように。
クラブという強い紐帯で結ばれたクラブが育つことを願っている。
恩師は、クラブの語源は「ゴルフクラブは、昔、一本一本の枝が寄り集まり一本にまとめられたものが、クラブと呼ばれた」と教えられた。
ムリに、総合型にすることもなく、やりたいというスポーツを支援することこそ大事だと思うのだが。少数派も、大事なのではなかろうか。