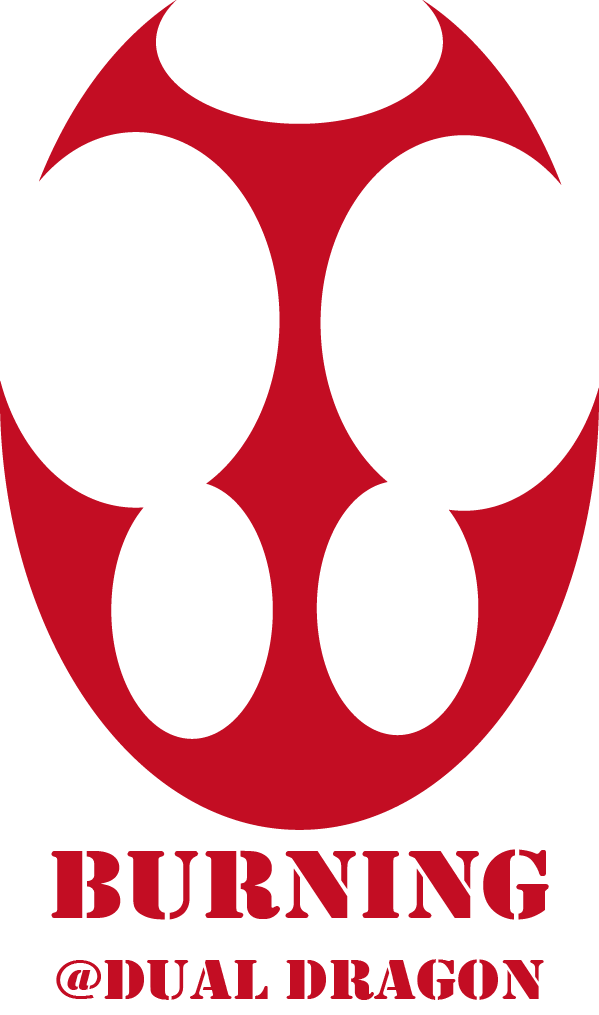2016/08/22 20:56
GAME CHANGER NZで模索されるラグビーゲームの変革!?
今年に入り、NZのラグビーがさらに進化をしたのではと考えています。全くの個人の見解ですが。RWC2011後のNZの活躍は凄まじいものでしたが、今年のNZもさらに、進化の模索をしています。昨年のSUPER RUGBYで活躍したハリケーンズが、ビッグネームの移籍により戦力ダウンを余儀なくされると考えられていましたが、すぐに後継者が見つかり戦力ダウンではなく、さらに戦闘能力が増しチャンピオンになりました。昨年度の闘いで印象に残るのは、とにかく、ボールを停滞させずに、動かし続ける。ボールを一番動かしたチームであったように、ブレイクダウンからすぐにボールを持ち出して攻撃し続けたことが印象的でした。それは、少ない人数でもボールを持ち出し、絡まれ、ターンオーバーされてもかまわないぐらいの徹底したボールを停滞させず、動かし続けるというものでした。どこまでもボールを動かし続けるので、プレイヤーのスタミナが心配でした。
今年のハリケーンズは、防御が恐ろしくラッシュアップで、トーナメントに入ると、勝ち上がってきた強敵を3試合すべてノートライに封じ込めるという防御の進化もみせました。
ハリケーンズで好きなプレイヤーは多くいますが、注目したいのは、フランカーのBrad Shields(Height 1.93 m、Weight 111 kg)です。他のバックローは、名前がすでに大きいですが、彼も注目していました。要所でよいタックル、防御をするからです。ただ、決勝戦では、彼が持ち込んだボールがクリーンアウトされず、ターンオーバーされるシーンが2つほどありました。「そんな攻撃力、ボールキャリアじゃ、AB’Sに呼ばれないぞ!」とその時考えていましたが、ボールを動かし続けるリスクを選択しているのです。ボールも人も速く動かす、ハイムーブ、ハイスピードデシジョンメイキング、リスクを恐れず闘っていました。
日本のチームは、テンポが速いときは速いですが、逆に、停滞に次ぐ停滞、安全に次ぐ安全とある意味かなり保守的に、ミスを恐れたり、攻撃のテンポを自ら止めるような場面にも出くわします。ボールを停滞させ安全にボールを保持するような場面がありますが、ラグビーの哲学が違うような気がします。
サンウルブズが、オーストラリアチームに完膚無きまでに力の差を見せつけられたときは、「戦術ループ」について行けなかったと無力感を感じました。試合中に戦術が変更されるとついて行けなくなると、力の差を痛感しました。
今、NZでは戦術を使い分けるだけではなく、戦術を越えた、戦術では補えない意志決定の領域において、GAME CHANGER(ゲームを変える)としてラグビーの質を変えようとしているのではと、NZの恐ろしさを感じる次第です。