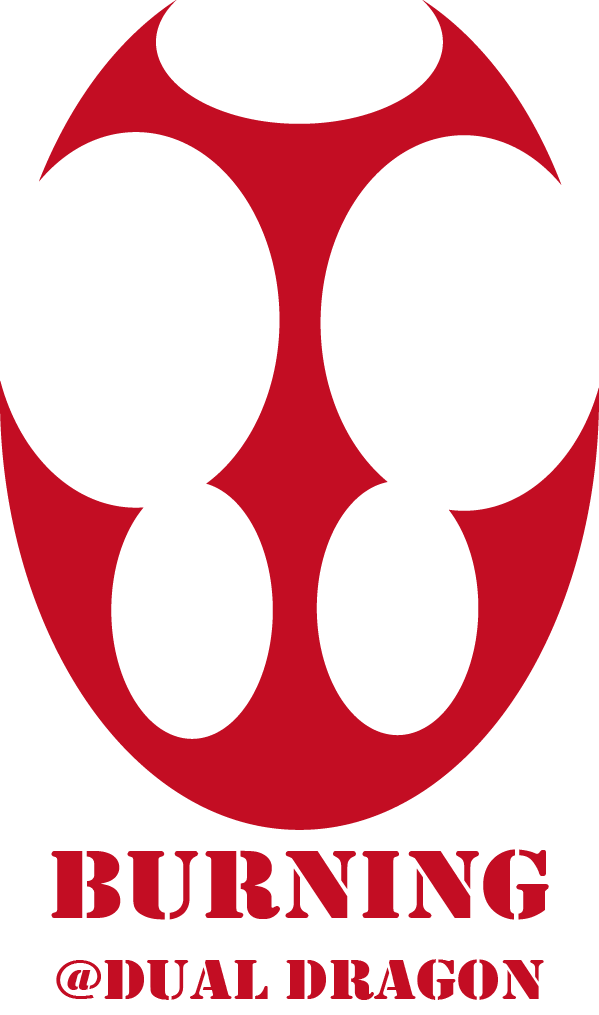2016/09/07 19:21
まどろっこしいタイトルですいません。
昨日2016.9.6日サッカーアジア予選があり、日本代表対タイ代表が対戦しました。ともに初戦を落として苦しい立場にある両チーム。最近、Jリーグのアジア戦略ということもあり、日本の影響を強く受けてめきめき地力を付けているタイ代表との試合でしたが、いたって凡戦。一方的に日本代表が攻撃しつつも、なかなか得点に結びつかなかったというものでした。
そして、翌日のラジオ番組に某サッカー評論家の登場となり、代表監督の手腕に疑問とプレイヤーに対する批判と「背骨のないスタイルで、何がしたいのか分からないサッカーになってしまっている。もっとスタイルを追求したサッカーをすべきだ」と訴えていました。
この辺にも、原因があるのだなと感じました。「代表監督は、臨機応変に対応するサッカーは特異だが、サッカースタイルはない」ようなことも行っていました。
残念です。武蔵の国の批評家としては残念です。
戦術を研究する人達の多くが、孫子の兵法と、宮本武蔵の五輪の書を研究するようです。近代に近い、クラウゼビッツよりも五輪の書だそうです。
孫子の兵法の「敵を知り、己を知れば、・・・」と「五輪の書」は、相通じるところがあります。現代のスポーツにも通じます。ただ、闘うことを回避できる闘いと、スポーツのように闘いを回避できない場合がありますが。ムサシが、闘いに明け暮れた日は、自身の戦い方に相手を引きずり込んで勝利をしたり、勝てる相手にのみ闘ったともいえるようです。雲隠れしていた時期に、何があったのか分かりませんが。
そして、翌日のラジオ番組に某サッカー評論家の登場となり、代表監督の手腕に疑問とプレイヤーに対する批判と「背骨のないスタイルで、何がしたいのか分からないサッカーになってしまっている。もっとスタイルを追求したサッカーをすべきだ」と訴えていました。
この辺にも、原因があるのだなと感じました。「代表監督は、臨機応変に対応するサッカーは特異だが、サッカースタイルはない」ようなことも行っていました。
残念です。武蔵の国の批評家としては残念です。
戦術を研究する人達の多くが、孫子の兵法と、宮本武蔵の五輪の書を研究するようです。近代に近い、クラウゼビッツよりも五輪の書だそうです。
孫子の兵法の「敵を知り、己を知れば、・・・」と「五輪の書」は、相通じるところがあります。現代のスポーツにも通じます。ただ、闘うことを回避できる闘いと、スポーツのように闘いを回避できない場合がありますが。ムサシが、闘いに明け暮れた日は、自身の戦い方に相手を引きずり込んで勝利をしたり、勝てる相手にのみ闘ったともいえるようです。雲隠れしていた時期に、何があったのか分かりませんが。
ゲーム分析の進んだ近代戦に於いては、OODAループといわれる、敵よりも先に判断をして機制を制するという闘いが主流となりつつあります。スタイルを分析され、丸裸にされた状態で、優位にゲームを進めることは難しいものです。正面突破型といいますか、スタイル、プラン重視型が良しとされるようです。それが通用するのかしないのか?
往年のムサシはどうだったか分かりませんが、闘いに明け暮れたムサシは、そんな闘いをしなかったように認識しています。
ムサシの勝つためにいかに行動するかを考え抜き実践した思考こそ重要ではないでしょうか!?
そうなれば、従来型の思考、コーチング方法では、限界です。
先日、トップリーグのプレイヤーについても考察しましたが、学生プレイヤーの方が適応が早く、トップリーグのプレイヤーの方が、すぐに適応できなくなっている。
これって、指示待ち!?考えることをしなくなったから!?と心配です。
往年のムサシはどうだったか分かりませんが、闘いに明け暮れたムサシは、そんな闘いをしなかったように認識しています。
ムサシの勝つためにいかに行動するかを考え抜き実践した思考こそ重要ではないでしょうか!?
そうなれば、従来型の思考、コーチング方法では、限界です。
先日、トップリーグのプレイヤーについても考察しましたが、学生プレイヤーの方が適応が早く、トップリーグのプレイヤーの方が、すぐに適応できなくなっている。
これって、指示待ち!?考えることをしなくなったから!?と心配です。