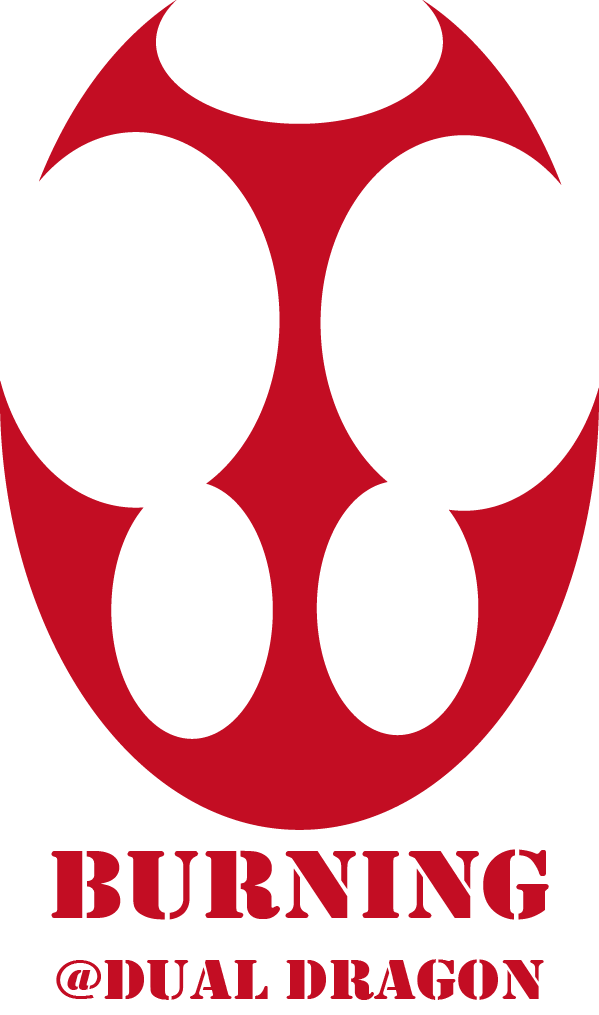2016/09/08 21:00
ご存じの方も多いかと思いますが、サッカー界に優秀なコーチがおりタイトルを席巻しました。彼の考え方には、共感を得ました。
「サッカーは誰のものか?」と飽き飽きする表現から思考がはじまっているようです。
彼は、眠っている、まだ目覚めていないプレイヤー一人一人の可能性を引き出し、そのチームにあったプレイモデルを確立するようです。
彼は、眠っている、まだ目覚めていないプレイヤー一人一人の可能性を引き出し、そのチームにあったプレイモデルを確立するようです。
そのためプレイヤーが学習できる環境を作ることが大事だと考えているようです。引用させてもらうと「教え込んで,やらせるのではなく、選手たちを受け入れて脳が学習できる環境を与える。彼らが成長でき、よりよい選手になれるように」とあります。ラグビーの指導者の方からは「そんなことを言っていても、日本のプレイヤーには、できない」「環境が違う!」などという意見がすぐに聞こえてきそうですが、では、「今のコーチングスタイルで、プレイヤーの能力は引き出されているのでしょうか!?」とプレイヤーを過小評価し、才能をコーチの考える範囲内で止め於いていることもあるかもしれないとは考えられないでしょうか?
coaching 2.0の考え方も、プレイヤーの学習する能力を大切にし、ゲーム中に自己解決する能力、これは、成長する環境をせめて残しておいてほしいと願っています。そのために、コーチに与えられた、ドリル中心のスキルは高められても、ラグビー理解は高められないトレーニングからも少しは、ラグビー学習できるコーチングスタイルへと変化してほしいと願っています。
coaching 2.0の考え方も、プレイヤーの学習する能力を大切にし、ゲーム中に自己解決する能力、これは、成長する環境をせめて残しておいてほしいと願っています。そのために、コーチに与えられた、ドリル中心のスキルは高められても、ラグビー理解は高められないトレーニングからも少しは、ラグビー学習できるコーチングスタイルへと変化してほしいと願っています。
「ラグビーは誰のものか?」
コーチやプラン遂行型(計画)というゲームではなく、プレイヤーのためのラグビーであってほしいものです。
コーチやプラン遂行型(計画)というゲームではなく、プレイヤーのためのラグビーであってほしいものです。