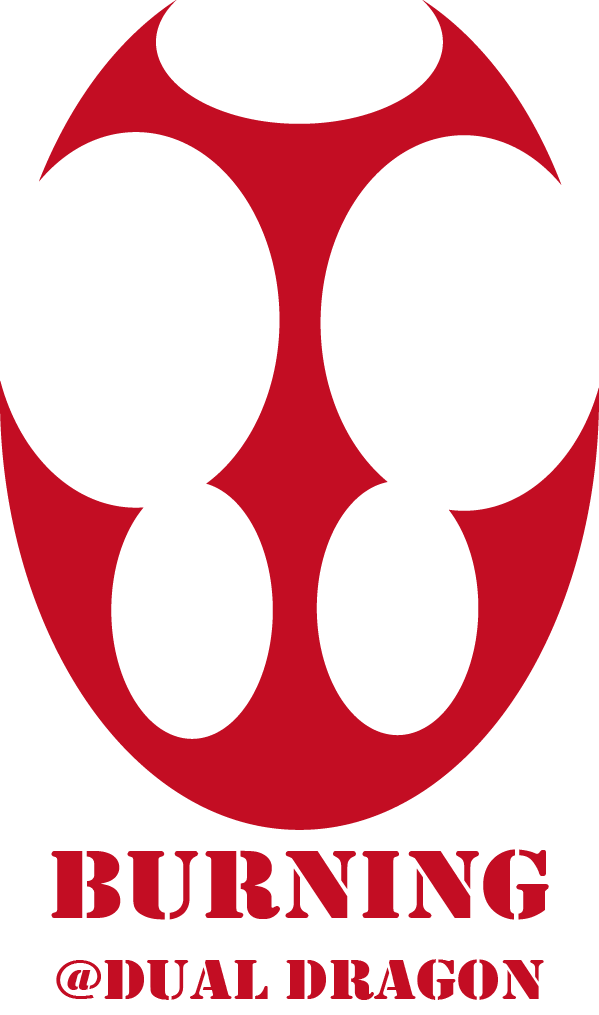2017/04/11 19:38
戦術セミナーでも少し話しましたが、このテーマは、20年来のテーマであったかもしれません。
日本のラグビーは、強いと昔から信じていましたが、結果が出ないので腑に落ちませんでした。はるか以前に作成したテキストも「日本には、共通とするコーチングマニュアルなどないから、選抜されたチームは、実力を発揮することなく脆く崩れる」ということを問題としていました。トップリーグや前代表監督が一つ改善してくれています。海外でも勝てるということを証明してくれています。
さて、「不確実な敵」「不確実な味方」ですが、これも軍事関連の書籍からですが、不確実というのは、正規軍ではなしにテロやゲリラ戦のことを指しています。ここでは、モダンラグビーのことであると考えています。ラグビーは、色々なプレイを仕掛けてきます。いくら分析しても、分析の裏をかいてきます。傾向がつかめてもすべてではありません。それゆえ、分析中毒という、分析に溺れることすらあります。過去の日本代表も、一時期、分析崇拝が講じて典型的な失敗の本質を犯した経験があります。
「不確実な味方」ですが、これは、選抜させたチームはどうしても、チームとしての熟成度が限られます。それでも結果を求められるので、味方ですら、「どのようなプレイをするのか」という不明瞭な部分があります。(チームとしては、化学反応を促す、活性化のために必要な要因という側面もあります)
この2要因から、コーチングのスタイルも考える必要があります。すべてコーチの指示待ちチームにしてしまうと、到底「不確実な敵」「不確実な味方」という状況下では、パニックに陥り、勝利を掴むことは遠のくでしょう。戦争では、それはすなわち死を意味するようで、軍隊では、はるか以前から、トップダウンの指揮系統が見直され、違う手法が取り入れられているようです。
プレイヤーに、意志決定をする権限をわたすコーチングが必要とされています。
coaching 2.0
プレイヤーに、意志決定をする権限をわたすコーチングが必要とされています。
coaching 2.0
はやく、現役のプレイヤーにcoaching 2.0を提供してあげてください。
きっと、社会人になっても通用するスキルを身につけることが出来るかもしれません。
きっと、社会人になっても通用するスキルを身につけることが出来るかもしれません。